津波による浸水状況について1号機から4号機は概ね明らかになっているが、廃棄物集中処理施設(プロセス主建屋等)や3号機・4号機開閉所の浸水状況は明らかではない。廃棄物集中処理施設における電源供給や復旧も不明である。

ところで廃棄物集中処理施設(プロセス主建屋)の電気設備は建屋の4階にあったようである。3.11津波による被水による機能喪失はなかったのではないか。もっとも外部電源などの受電はできなかったと思われる。
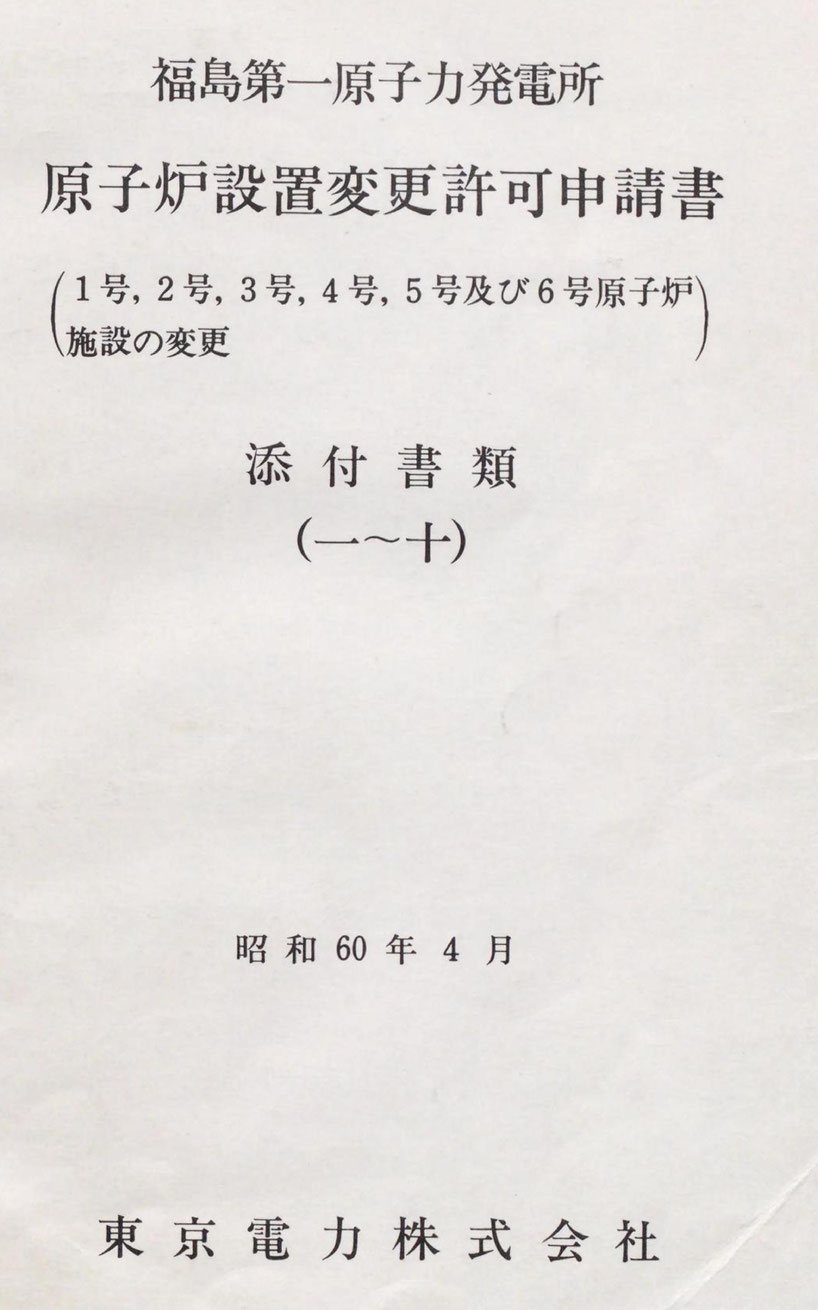

事故後の東京電力の説明資料によると、プロセス建屋常用M/Cや後備M/Cは機能維持をしているようであり、事故後の電源復旧に利用されているように思われる。




福島第二では、事故直後に電源車と廃棄物処理建屋の配電盤から仮設ケーブルを海水熱交換器建屋まで敷設し電源復旧をしている。

仮に南側に主眼を置いた防潮堤だけが設置された場合でも、敷地南東側の浸水は1メートルにも見たなかったようであり、廃棄物集中処理施設、共用プール建屋あるいは4号機・3号機の浸水も、全くの無防備であった3.11時よりは軽減されたことになるのは明らかである。がれきの散乱なども施設南側ほど少なかったのではないか。

そして福島第二と同様に廃棄物集中処理施設等のM/Cを利用して仮設ケーブルを敷設し、1号機から4号機の電源復旧が早まったのではないか。3.11においても2号機の電源車とP/Cを利用した電源復旧が行われ作業完了に近づいていたようであるが3月12日午後3時の1号機の水素爆発により、作業はやり直しとなってしまった。M/Cが利用できれば事故は防ぐことができたと政府事故調技術解説でも指摘されている。

電源設備を4階に設置する着想はプロセス主建屋では行われており(海岸に隣接して設置されているからであろうか)、せめて1号機のM/Cや電気品室を2階に上げるか、海岸に面する大物搬入口のすぐ後ろではない場所に設置するか、津波警報時には防護扉を閉めるだけでも事故の進展は異なった蓋然性が高い。